ドローン検定3級を取得した方!!ドローン検定2級目指してみませんか?
ドローンインストラクターを目指している私は、ドローン検定公認指導員の取得条件のドローン検定2級を取得を目指し勉強を始めました。
ここでは、ドローン検定2級の【リスク管理】をなるべく丁寧に記載させていただきます。少しでも参考になればうれしいです。
目次
リスクの種類
【リスク】とはある状況において、その【危険性】を表す言葉です。
すでに故障しているものは含みません。すでに故障しているものはトラブルです。
リスクは大きく2つに分けられます。それは【他者に危害を与えるリスク】と【その他のリスク】です。
他者に危害を与えるリスク
運航を管理する上で最も重要なことは【他者に危害を与えるリスク】を最小限に抑えることです。
墜落のリスク
まず思い浮かぶのは【墜落のリスク】です。
機体が落下し地上の物件に衝突した場合、その物件を破損してしまう恐れがあります。物件ではなく人の場合けがを負わせてしまう恐れもあります。
アンコントローラブルは、機体のトラブルに起因するものだけではありません。飛行環境によってもそのリスクを伴います。
風速が安定しないときなどは、突風に見舞われる危険が生じます。天候によっては、突然雨が降り出すこともあるかもしれません。雨による機体内への水漏れや風により制御装置にトラブルが生じアンコントローラブルになり墜落するということも考えられます。
電波障害のリスク
これは、他者に危害を与えるリスクと同時に自分が電波障害を受けるリスクもあります。
複数の無線装置がお互いに影響を及ぼしあう危険が常に付きまといます。ドローンはほとんどの制御を電波に頼っています。(GPS、操縦の無線通信)これらが機能しなくなると墜落待ったなしです。
機体によっては通信が切れたときにGPSを使い離陸地点に自動帰還機能を持ったものもありますが、そのGPSも機能しなくなる可能性も考えなくてはなりません。
稀なケースですが、強い送信機の電波が医療機器に影響を及ぼす可能性もあります。

航空交通やその他の交通リスク
飛行機や無人航空機が飛び交う環境を【航空交通】と呼びます。許可申請の必要な空港の周辺の飛行や、地上150m以上の飛行の情報は管轄の航空事務所を通じ空港の管制所も把握することになっています。つまり申請に沿わない飛行を行うことは航空交通に影響を及ぼすリスクが非常に高いということとなります。
また、航空周辺は非常に強い電波が飛び交っているため、電波障害を受けるリスクも非常に高いと考えなくてはなりません。
その他のリスク
機体に関するリスク
運搬時に機体を損傷させてしまうリスク、適切な保護を行って運搬してください。
業務遂行にかかわるリスク
機材の忘れ物、バッテリーの充電不足などの業務が遂行できないリスク。
バッテリーや燃料に関するリスク
前々項「絶対合格‼【ドローン検定2級】資格取得|バッテリー」で触れているように、ドローンのバッテリーは、発火や爆発などのリスクがあります。保管方法や運搬方法に十分な注意が必要です。
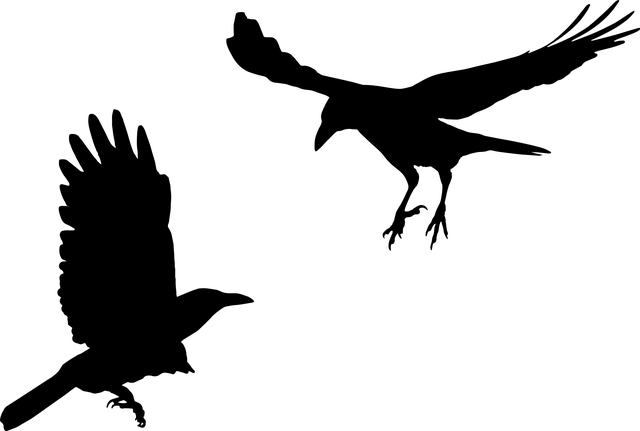
飛行妨害を受けるリスク
忘れがちですが、飛行中に鳥獣類や攻撃を受けるリスクや、着陸地点に人または障害物が進入してしまうリスクも考えられます。実際にカラスやトンビといった鳥類と接触し墜落した事例もあります。また見物人などの可能性も考慮し、離着陸地点や飛行ルートなどに立ち入り禁止措置を行う必要も考えなくてはいけません。
リスク分析
| 高リスク | ①人にけがを負わせる危険 |
| ↑ | ②ほかの交通に障害を与える危険 |
| ↑ | ③他者の物件に損傷を与える危険 |
| ↑ | ④関係者の物件に損傷を与える危険 |
| 低リスク | ⑤その他の危険(機体のロストなど) |
危険の評価を行い危険性の高いほどリスクが高い事象であると考えます。なおかつ複数の危険が伴う場合より高いリスクの可能性を評価するようである。
例えば、飛行許可を得た操縦者以外誰もいない広い田んぼと住宅地付近の河川敷では後者の方がリスクが高いことがわかります。
テキストでは、【高速道路】を例にあげています。高速道路では上の表の①②③⑤が該当するので大変危険だということがわかります。加えて、そのリスクは機体の性能によって増減しないということです。
リスクマネジメント
【リスクマネジメント】とは、実際にトラブルが生じた際にどのような対処を取るべきか手順を定めておくことです。さらに重要なのでは、被害をできるだけ小さくすることです。
トラブル内容はもちろんですが、危険性がどの程度高まった場合に対処するかの基準を定めることも重要です。より多くのリスクを事前に想定しておきましょう。
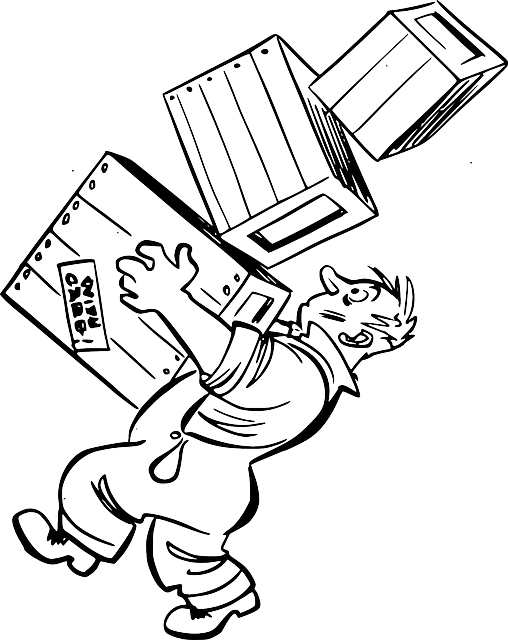
安全領域の計算
飛行中に機体が落下しうる範囲を【安全領域】と呼び、その範囲に人や物が立ち入ることが無いようにする必要がある。そしてその範囲はより大きく確保する方が良い。
安全領域の計算では、空中で水平移動中でトラブルが生じ、アンコントローラブルの状態で墜落(自然落下)することを想定します。よって計算方法には3級で学習した「自然落下」を用います。
なお、高度が高くなる、対地速度が速くなると安全領域はより広く取る必要がある。
※計算に用いる速度は対地速度でなければなりません。
なお、催事上空での飛行させる場合、国土交通省の規定により飛行速度に関わりなく、飛行の高さに応じて一定範囲以上の立ち入り禁止区域の設定が必要である。(同テキストP134後に航空法で触れます)



コメント